お墓を生前購入する!現状、メリットとデメリット
「先祖代々のお墓に入る」という人以外にとって重要となるのが、「お墓の購入」です。お墓はかなり値段の高いものであり、一財産と言ってもよいほど。このため、「生前購入」という方法を検討する人もいます。
この「お墓の生前購入」について、その現状とメリット、デメリットについて見ていきましょう。


納骨堂辞典 > 納骨堂コラム > お墓・お葬式・供養 > 家族葬、直葬に喪主挨拶は必要?いろんな葬儀の喪主挨拶文
喪主挨拶というのは、喪主を務める人が参列者に向けて行うものです。経験したことがあるという人はあまりいないでしょう。そこで、一般葬や家族葬、社葬など様々な葬儀形態に合わせた喪主の挨拶のポイントと定型文をご紹介します。
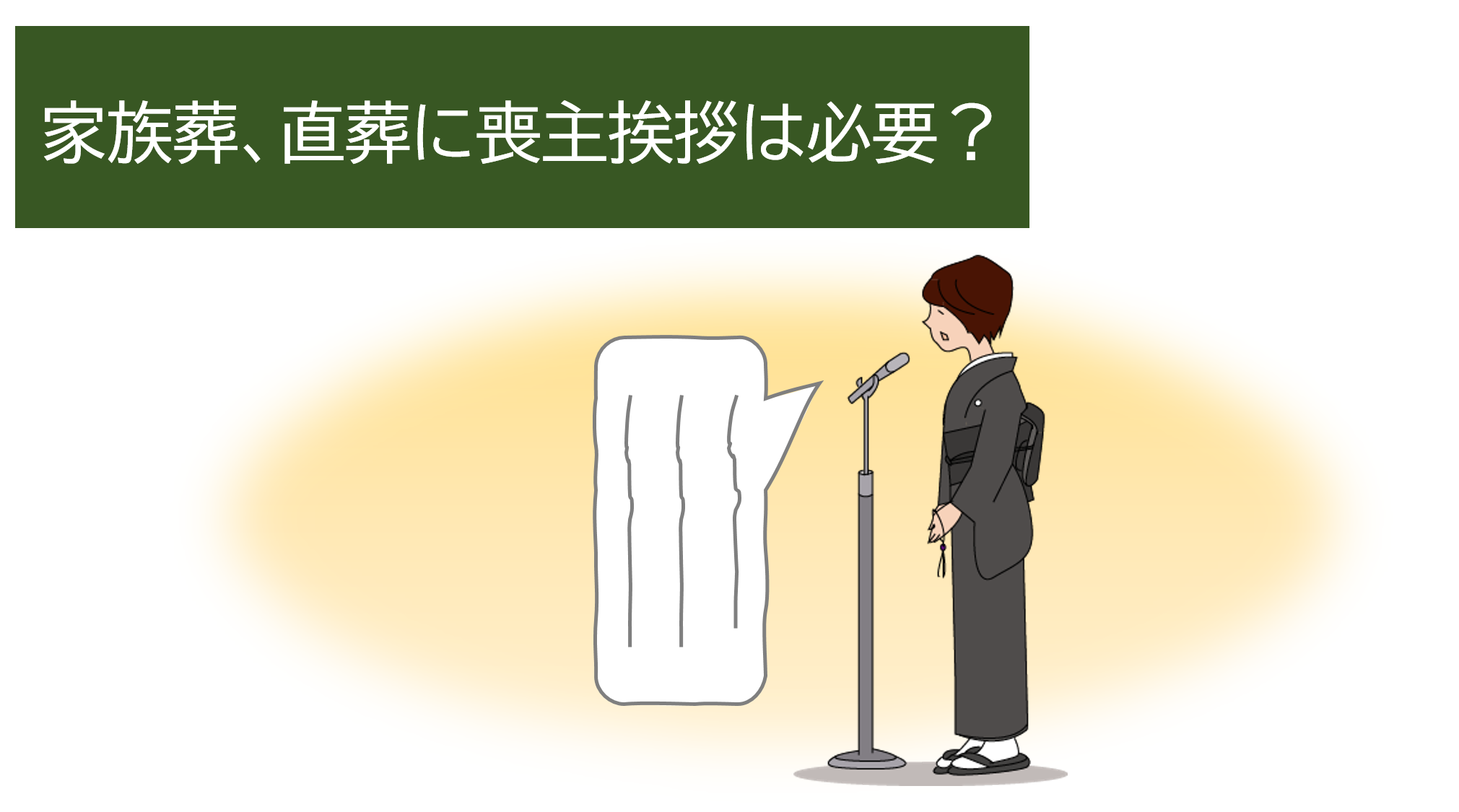
葬儀の場で挨拶を行うのは、誰でも不慣れなものです。だからこそ、挨拶文には長く使われてきた定型があり、マナー本を開いたりネットを検索したりすれば、簡単に参照することができます。ただ、最近では、会社関係やご近所などは参列せず、ごく身内だけで葬儀を行う家族葬を選ぶ人が増えてきました。すると、「本日はこのようにたくさんの方々にお集まりいただき……」といった定型文をそのまま使うのは不自然です。喪主自身よりも年上、目上の人が参列していないのに「今後もご指導、ご鞭撻を賜りますよう……」と頭を下げるのも、違和感があります。身内だけの葬儀では、どんな挨拶がふさわしいのでしょうか。まずは一般葬の挨拶をご紹介してから、親族のみの家族葬、葬儀をせずに火葬だけを行う直葬、そして様々な立場の人が集まる社葬における喪主挨拶の定型文をご紹介します。
親族だけではなく、会社関係や友人関係など幅広く人が集まる一般葬では、旧来の定型文をそのまま使うことができます。まずは会葬へのお礼を述べ、生前の交流に対して故人のかわりに感謝します。その後、故人の人となり、心に残るエピソードなどを手短に話す人もいることでしょう。最後には、今後も遺族と変わらないお付き合いをしてもらえるようお願いして締めます。
家族葬の喪主挨拶では、一般葬の挨拶から不自然と思われる文章を省くことになります。しかし、ただ短くするだけでは素っ気ない挨拶になってしまいますので、より親密さを感じる表現に差し替えるのがポイントです。故人にまつわるエピソードは、身内だからこそ想い出を分け合えるようなものを選ぶと、ぐっと家族葬らしくなります。ただ、あくまで儀式の最中なので、長々と思い出話をするのは避けましょう。
葬儀をせず、火葬だけを行う直葬では、当然ながら葬儀時の喪主挨拶はありません。火葬場で炉入れとなった直後や、収骨を行った後など、参列者が解散する直前に、喪主としてご挨拶をすると場が締まります。
社葬は、家族葬や直葬とは対照的に、さまざまな立場の人が参列する場です。仕事上のつながりがある人が大半なので、関係者への感謝の気持ちや、家族から見た故人の仕事に対する姿勢などを意識して盛り込むようにしましょう。先に葬儀委員長などが丁重な挨拶を済ませていることも多いので、簡潔な挨拶で十分です。今後、親族が代表を受け継ぐような場合は、喪主挨拶をもってその宣言をすることもあるでしょう。
以上、さまざまなケースの喪主挨拶例をご紹介しました。喪主挨拶の文章は、定型を参考にしながらも、自分と参列者の関係性を考慮してアレンジするのがポイントです。参列者の心に残る喪主挨拶ができるよう、しっかりと準備しておきましょう。原稿を読み上げるスタイルでも構わないので、ゆっくり、はっきりと感謝を伝えることが重要です。
納骨堂辞典では東京や関東の納骨堂の紹介をしています。みなさんのご要望にお応えして人気ランキングや費用、納骨堂の種類についてなども解説していますのでぜひご覧ください。納骨堂辞典|納骨堂・永代供養墓の全て
「先祖代々のお墓に入る」という人以外にとって重要となるのが、「お墓の購入」です。お墓はかなり値段の高いものであり、一財産と言ってもよいほど。このため、「生前購入」という方法を検討する人もいます。
この「お墓の生前購入」について、その現状とメリット、デメリットについて見ていきましょう。
お正月を機に実家に帰り、「せっかくだからお墓参りでも」と考えている人はいませんか。お正月は、お墓参りにふさわしい時期です。しかし、さまざまなことに気をつけなければ、風習のタブーに触れてしまう場合があります。お正月にお墓参りをすべきか否か、するとしたらどんな注意点があるかについて解説します。
この頃では、各地に「お別れ会」を企画する葬儀社が目立つようになりました。「葬儀」や「告別式」ではなく、「お別れ会」の案内がきたことのある人は、「お葬式とどう違うのだろうか?」と首をかしげたこともあるでしょう。ここでは、葬儀よりもカジュアルな、お別れ会について解説します。
葬儀があると、戒名を授かるということをご存じの方は多いでしょう。この戒名を授かるときのお布施が高額といううわさを聞き、「戒名って本当に必要なの?」と疑問に思っている人はいませんか。戒名の授かり方は、だんだん変わってきています。戒名の意味や、最新の授かり方についてお伝えします。
仏事や弔いの場として捉えられるお寺やお墓。最近、いままでのイメージを一新するような、新たな価値を提供するお寺やお墓が増えています。本記事では、ユニークな発信を行うお寺・お墓の中から、4つの魅力的な取り組みをご紹介します。
第1位

第2位

第3位

第4位

第5位

