グリーフケアとは?死別を乗り越える為のサポート
グリーフケアという言葉を耳にしたことはあるでしょうか。これは人の死を乗り越えられずにいる人を助ける支援という意味です。欧米では盛んにこのグリーフケアが行われ、ケアを行う側の教育も充実しています。今回はこのグリーフケアについて迫り、どのようにして悲しみから立ち直ることができるのか、周りの人はどうしていけばいいのか、見ていきましょう。


納骨堂辞典 > 納骨堂コラム > 用語・豆知識 > 喪主と施主の違いを解説。頼まれた時のために知っておこう
喪主を務めなければならない機会は、多くの人にやってきます。しかし、葬儀においては喪主だけではなく「施主」も大切な仕事です。大抵は兼任することになるため誤解されがちですが、本来喪主と施主はまったく別の役割なのです。ここでは、喪主と施主の違いについて解説します。
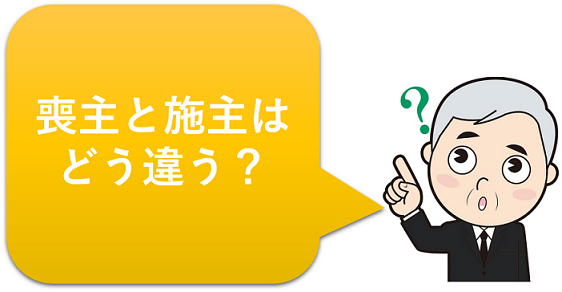
喪主と施主の特徴を簡単に説明すると、以下のようになります。
喪主は遺族の代表者であり、葬儀全体の責任者です。参列者へのあいさつと弔問の受付、葬儀の開始時や出棺時のあいさつ、葬儀社との打ち合わせなど多くの役割を担います。一般的には、故人の配偶者もしくは子の代表が喪主を務めます。
施主は葬儀の費用を負担する人です。喪主のサポートも行い、葬儀の運営面での代表を務めます。葬儀に限らず、催し物で費用を負担する人は基本的に施主となります。喪主と施主が混同されやすいのは、「葬儀の費用は喪主が出すもの」という認識の人が多いためでしょう。実際、喪主が施主を兼任する場合は、単に喪主と呼ぶのが一般的です。
喪主と施主が混同されがちな理由は、戦前と戦後の制度の違いにあります。かつての民法では、嫡出子の長男が戸主の財産権と祭祀権をすべて相続することになっていました。長男が非常に強い権限を持っていたわけです。財産権は文字通り一家の財産を管理する権利で、祭祀権はお墓・遺骨・仏壇などを管理する権利のことです。この2つの権利を長男が独占しているため、喪主と施主を分ける必要はありませんでした。葬儀の一切も長男が取り仕切っていたのです。しかし、戦後の法改革により、長男がすべてを独占する制度は否定されました。財産権と祭祀権は分離され、きょうだい全員が平等に扱われるようになり、喪主と施主が同じ人である必要もないと考えられるようになったのです。
現在では、法律上は誰が喪主・施主を務めても構わないことになっています。きょうだい全員が喪主を務めることも可能ですし、費用を分担するのも自由です。それでも喪主と施主が混同されやすいのは、長男がすべての責任を追っていたかつての制度の名残だと考えられます。
喪主と施主は、同じ人が兼任しても、別々の人が担当しても構いません。ただ、現在でも特に理由がなければ兼任するのが一般的です。では、喪主と施主を別々の人が担当しなければならないことはあるのでしょうか。考えられるケースとしては、以下のものがあります。
たとえば、喪主は故人の配偶者が務め、葬儀の費用は故人の子が負担するケースは珍しくありません。親子が別々に暮らしており、子の方が経済的な余裕がある場合は、喪主と施主を分ける意味があります。
経営者が亡くなった時などに行う社葬では、費用負担を会社が負担するのが普通です。そのため、形式上会社(法人)が施主となります。
喪主を長子が務めるなら施主には次子がなるというように、親族の平等を考えて役割を分担することもあります。喪主・施主を務めるということは親族内での立場をアピールすることにもつながるため、大きな家では誰が喪主・施主になるかで揉めることさえあるのです。早い段階で相談しておいた方がいいでしょう。
喪主と施主は、個人の葬儀ではあえて分ける必要がないことも多く、それぞれの意味を知らない人も増えています。しかし、親族の平等感を出すために、喪主と施主を分けるよう求められることがあるかもしれません。葬儀の準備で手間取らないように、概要を知っておきましょう。
納骨堂辞典では東京や関東の納骨堂の紹介をしています。みなさんのご要望にお応えして人気ランキングや費用、納骨堂の種類についてなども解説していますのでぜひご覧ください。納骨堂辞典|納骨堂・永代供養墓の全て
グリーフケアという言葉を耳にしたことはあるでしょうか。これは人の死を乗り越えられずにいる人を助ける支援という意味です。欧米では盛んにこのグリーフケアが行われ、ケアを行う側の教育も充実しています。今回はこのグリーフケアについて迫り、どのようにして悲しみから立ち直ることができるのか、周りの人はどうしていけばいいのか、見ていきましょう。
仏教にはさまざまな宗派があります。ここでは、インドで興った仏教が中国を経て日本へやってきた歴史とともに、日本における伝統的な仏教の十三宗と、奈良時代に栄えたいくつかの宗派について解説します。
身内の死は誰にとってもショックなものです。特に親となると生まれた時からずっと近くにいてくれた存在として喪失感や悲しみはなおさらのこと。母親の死ならば父親、また、父親の死ならば母親も悲しみに暮れるはずです。しかし、そんな中でも急を要する手続き・やるべきこと(葬儀など)を冷静に行わなくてはなりません。もしもの時に慌てないようどのような手続き・やるべきことがあるのかを知っておきましょう。
ある程度年数の経ったお墓の後ろには、木の板が何本も立てられていますよね。自分がお墓を守る番になると、「あれは立てなければならないものなのか?」と迷う人もいるでしょう。塔婆を立てて故人の成仏を祈る、塔婆供養について解説します。
「遺品整理サービス」とは故人の遺品を整理してくれるサービスです。もし急逝してしまったら、その後の自宅の後片付けなどは家族や親族にお願いするしかありませんでしたが、遺品整理サービスを利用すれば負担が軽減され気持ちの整理もしやすくなることでしょう。実際のサービス内容を詳しく見てみましょう。
第1位

第2位

第3位

第4位

第5位

