墓じまいでよくあるトラブル事例3つ
お墓の継承者がいない、お墓がある場所から遠方に住んでいるため、管理が大変という理由から墓じまいをする方が増えています。しかし、無縁墓にならないようにと墓じまいをするつもりが、思わぬトラブルに発展してしまうことが多々あるようです。今回は墓じまいにおけるトラブル事例について紹介します。


納骨堂辞典 > 納骨堂コラム > 用語・豆知識 > 無縁墓とは?承継者不足の日本の現状と解決策
「無縁墓(むえんぼ)」という言葉を耳にすることがあるかと思います。この「縁」とは、血縁や姻戚関係がある「縁故者(えんこしゃ)」の「縁」です。弔いをしてくれる縁故者のいないお墓のことを、無縁墓と言うのですが、現在それが日本各地に増えています。今回は、この無縁墓問題について紹介します。
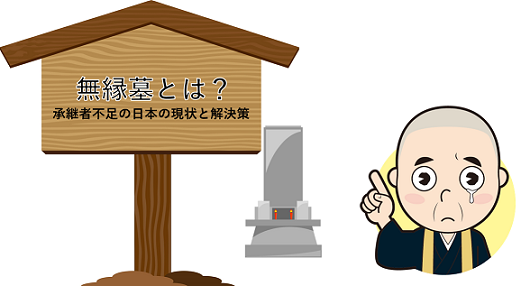
無縁墓とは、お墓を守り、お参りや法要、掃除、管理料の支払いなど、先祖供養のための世話をする人が居なくなったお墓のことです。つまり、そこに埋葬されている人と血縁や姻戚関係にある墓守(はかもり)が不明になり「無縁」となってしまったお墓です。法律上の正式名称は「無縁墳墓(むえんふんぼ)」※といいます。先代からお墓を受け継ぐことを特に承継とよび、その受け継ぐ人は「承継者(しょうけいしゃ)」と呼ばれます。明治政府によって家制度が整備されてから、昭和の時代までは家墓(いえはか)が中心であり、一つのお墓に一つの家族、親族が葬られ、墓守としてお墓を守り承継していくのは、長子の役割でした。しかし現在、承継者不足に悩む家が増えているというのです。一体なぜなのか、次項でその背景に迫ります。
※「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第三条より「死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)」
無縁墓の増加=承継者不足の背景には、家制度の崩壊、少子化とそれに伴う核家族化、個人主義の台頭、超高齢化社会、地方の過疎化など、様々な要因が絡んできます。ここでは、その一つ一つを紐解いていきます。
一家に一戸主を置き、代々その家を継承していくという明治期から続いた家制度は、戦後の民法改正を機にその実態は無くなりつつあります。家制度時代は、家長は父親で長男は家の跡取りとして育てられ財産を相続する代わりにその家の統率を執り、墓守もしていました。現在でも多くの家で長男長女が家を継ぐという流れはありますが、昔ほど「家を継がなければいけない」「家を守らなければいけない」という意識を持つ人が少なくなっているのも確かです。そうした家への帰属意識の低下により、お墓を承継しないという選択をする人、承継しても管理をせず放置してしまうという人が現れています。
現代の日本では少子化に伴い、父親と母親一組に対し子供は一人、という核家族化が進んでいます。核家族化が進むと何が起こるかというと、例えば一人っ子同士が結婚した場合は双方の先祖の墓を守らなければいけなくなってしまいます。お墓を二つ維持していくという事は管理費一つとっても倍かかり、年に数回互いの墓参りをするというのも大変です。また、女性の場合は、自分自身が配偶者側の家墓に入ることになる人も多いので、承継者がいなくなってしまうという事態も起こります。
前述した「女性は配偶者側の家墓に入る」と矛盾するようですが、個人を大事にする個人主義の台頭と合わせて「姑や夫と同じ墓には入りたくない」と考える女性も出てきています。さらに「○○家の墓」と彫られた画一的なスタイルではなく、独自のデザイン性を持った自分用のお墓が作りたい、という方は男女問わず存在するようです。
平成24年版の総務省の政策白書(日本の現状分析と将来の展望をまとめた報告書)によると、高齢化率(高齢人口の総人口に対する割合)は2010年(平成22年)の23.0%から、2013年(平成25年)には25.1%で4人に1人を上回り、50年後の2060年(平成72年)には39.9%、すなわち2.5人に1人が65歳以上となることが見込まれている※2そうです。高齢者の割合が増えると、次の世代となる若者の負担も増えていき、高齢者自身が承継者となることも往々にしてあります。高齢による体力の衰えによってお墓を守っていくことが現実的に難しいとなってしまう場合もあるでしょう。
※2 「少子高齢化・人口減少社会」総務省|平成24年版 情報通信白書
戦後の高度経済成長期に大量の人が地方から都市部に流入し、その結果、都市部への人口の一極集中が起こり、地方の過疎化が進みました。若者が都市部に出て行ってしまい、地方の高齢者はお墓と共に取り残され、やがてお墓は無縁墓となる、という事態が発生しています。今でも都市部に住みながらも地方の墓守をしているという人は多くいますが、遠方のお墓の管理が大きな負担となっている人も少なくありません。
こうして無縁墓になってしまったお墓は、その後どうなるのでしょうか?次項で説明していきます。
無縁墓になってしまったお墓はまず、行政やそのお墓を管理している宗教団体によって、承継者候補となる縁故者がいないかどうかの探索が行われます。そして、1年間の立札設置、官報公告(公告=広く知らせること)や各種書類提出を行った後でもなお承継者が見つからなかった場合は、お墓は撤去され、遺骨は合祀墓(ごうしばか・ごうしぼ)などに改葬されます。とはいえ、きちんと合祀・供養されるかは管理者次第になり、何よりお墓の撤去にも手間や費用はかかり墓地管理者に迷惑をかけてしまうことになります。先祖や故人の供養のためにも、今までお墓を守ってもらったお寺などの管理者へ恩を仇で返すという事態にしないためにも、管理ができない状況となったら無縁墓になる前に墓じまいや改葬などの適切な対応をするべきでしょう。
自分の死後に無縁墓を作らないためにはどのようにしたら良いのでしょうか。その手立ての一つは、今のお墓を無くし(これを「墓じまい」といいます)、承継者が居なくても永代供養をしてもらえるところに改葬(お墓のお引っ越し)することです。例えば、北欧のノルウェーにおいては、管理を行政の墓地課が行う合祀墓があります。記名もせず、区画内のどこかに遺骨を埋め、記念碑を立てて合同でお参りなどが出来るようにしています。ここまで極端ではなくても、他の人と同じ一つのお墓や納骨堂に合祀する形で、宗教法人やお墓の管理者が供養と管理をしてくれる永代供養墓もあります。価格は、平均で30万~50万円程度です(お墓の形態によります)。また、樹木葬という選択肢を取る人も増えています。自分用の区画に遺骨を埋葬し墓石の代わりに木を植えるという墓地の在り方です。
さらに、承継者不足の問題のところで取り上げた「一人っ子同士の結婚で守らなければいけないお墓が増えた」場合ですが、どちらかの、あるいは双方のお墓を墓じまいし、もう片方のお墓に改葬する、あるいは新しくお墓を作ってそこに改葬する、という方法もあります。この時気を付けなければいけないのは、双方に宗教の違いがある場合です。それを理由に片方のお墓への埋葬が拒否される可能性があります。その時には、後者の「新しくお墓を作る」という選択肢を選び、さらに宗教宗派不問の所にする必要があるでしょう。
いかがでしたでしょうか。最近終活がメディアで話題になり、お墓について関心を持つ人も多いのではないでしょうか。自分らしいお墓を模索していらっしゃる人も少なくないでしょう。「家族に面倒をかけたくない」という理由で、個人のお墓を希望する方もいらっしゃるでしょう。しかし、本来「お墓を作る」という行為は、自分がそこに居た証を残すという事で、お墓という形を取るのであれば基本は残り続けるものです。それを守り、供養してもらうことを望むのならば、どうしても誰かに面倒を見てもらわなければなりません。終活をされる際は、その誰かを誰にするのか、また、費用面ではどの程度の負担になるのかまで考えておくとよいのではないでしょうか。
関連記事:改葬はお墓の無縁化を防ぐ手段
納骨堂辞典では東京や関東の納骨堂の紹介をしています。みなさんのご要望にお応えして人気ランキングや費用、納骨堂の種類についてなども解説していますのでぜひご覧ください。納骨堂辞典|納骨堂・永代供養墓の全て
お墓の継承者がいない、お墓がある場所から遠方に住んでいるため、管理が大変という理由から墓じまいをする方が増えています。しかし、無縁墓にならないようにと墓じまいをするつもりが、思わぬトラブルに発展してしまうことが多々あるようです。今回は墓じまいにおけるトラブル事例について紹介します。
「リビングウィル」とは英語で”Lliving Will”となり、生前の意思という意味です。つまり、主に延命治療についての自らの希望になります。しかし、どうやって決めたらいいかなど、詳細はわからない人も多いのではないでしょうか。最近では葬儀やお墓についての内容が含まれることもあるそうです。ここれでは、より良いリビングウィルを行うために、基本事項と昨今の現状について説明したいと思います。
我々日本人にとって、仏式でお葬式をし、寺院が管理する墓地に納骨されるのは、いたって一般的なことです。しかし、他の宗教の人からすれば、決してそうではありません。夫婦間で宗教が違うとき、お墓はどのように選べばよいのか。その解決策について、詳しく解説します。
身内の死は誰にとってもショックなものです。特に親となると生まれた時からずっと近くにいてくれた存在として喪失感や悲しみはなおさらのこと。母親の死ならば父親、また、父親の死ならば母親も悲しみに暮れるはずです。しかし、そんな中でも急を要する手続き・やるべきこと(葬儀など)を冷静に行わなくてはなりません。もしもの時に慌てないようどのような手続き・やるべきことがあるのかを知っておきましょう。
「エンディングノート」とは自分の人生の最後の期間や死後について書き記すノートのことです。ここ数年多くの人が記されているというエンディングノート、それはいったいどんなものなのでしょうか。また、どんな内容をいつ、書くものなのでしょうか。こちらについて紹介します。
第1位

第2位

第3位

第4位

第5位

